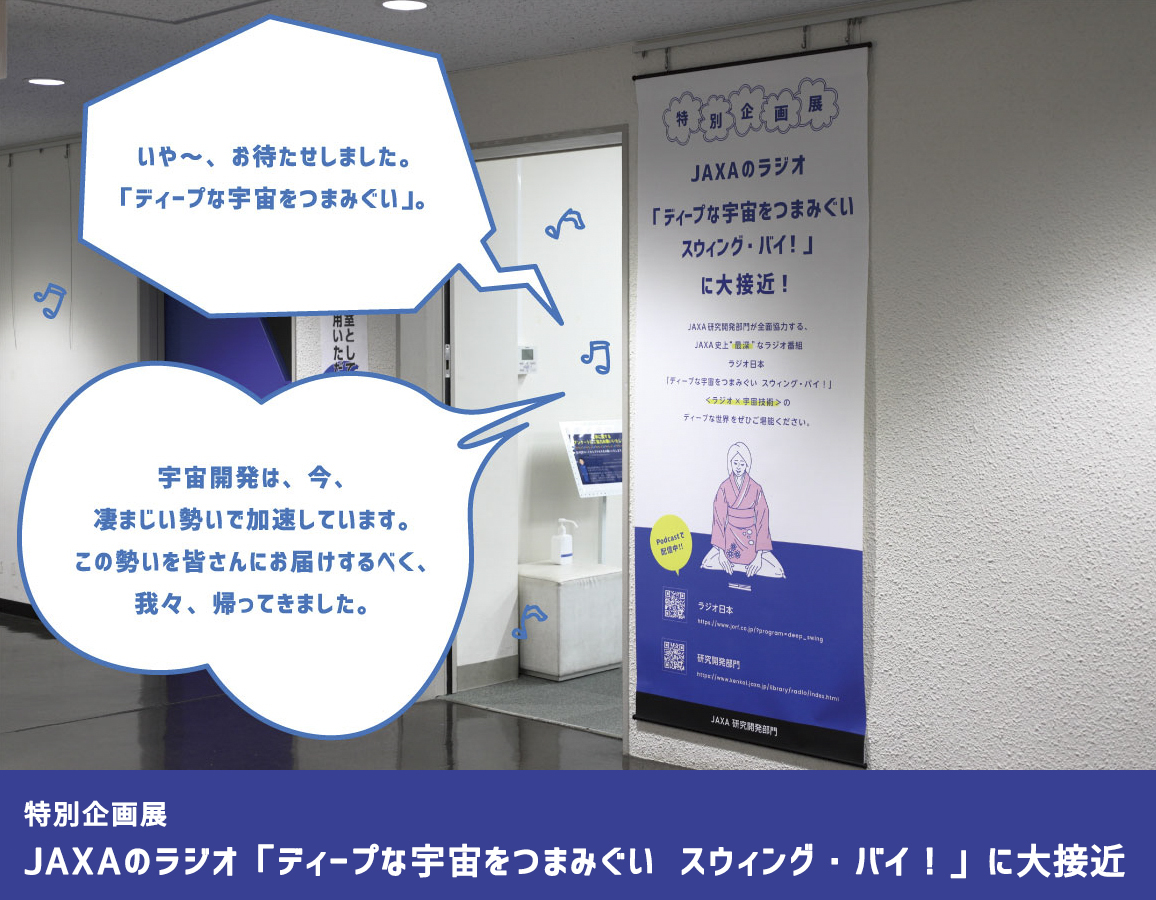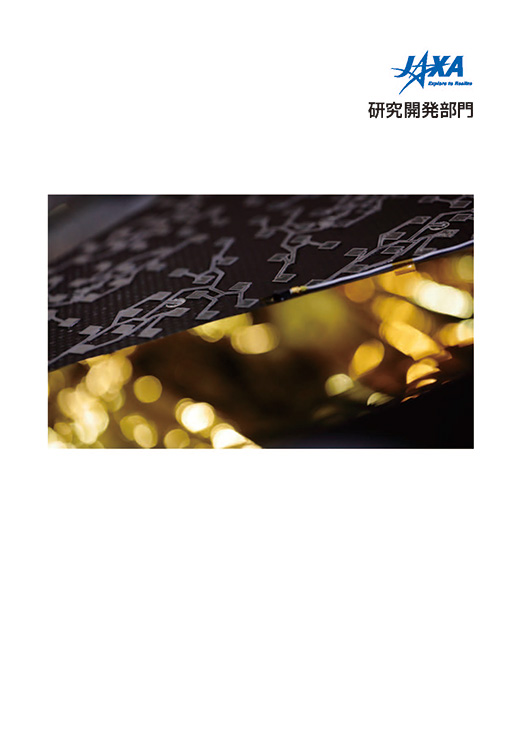2月24日(水) 9:30開場
| 開始時間 | 講演タイトル | 講演者(所属) |
|---|---|---|
| 10:00 | 開会挨拶 | 張替正敏(JAXA) |
| 10:05 | JAXAのスペースデブリ関連活動紹介 | 山中浩二(JAXA) |
| 10:35 | JAXA追跡ネットワーク技術センターにおける宇宙状況認識に関する活動の現状 | 渡邊優人(JAXA) |
| 10:55 | 換気休憩 | |
| 11:00 | JAXA 商業デブリ除去実証(CRD2:Commercial Removal of Debris Demonstration)の最新状況 | 山元透(JAXA) |
| 11:20 | JAXAスペースデブリ発生防止標準JMR-003の最新状況 | 佐藤健一(JAXA) |
| 11:40 | 昼休み | |
| 13:00 | パネルディスカッション 「日本の民間デブリ関連ソリューション事業化に向けた 挑戦」 |
モデレータ:上野浩史(JAXA) パネリスト: 蔵本順(ALE) 田治米伸康(アストロスケール) 中村友哉(アクセルスペース) 泉山卓(IHI) 久保田伸幸(KHI) 八田真児(MUSCATスペース・エンジニアリング) 福島忠徳(スカパーJSAT) 金澤誠(Space BD) |
| 14:55 | 休憩 | |
| 15:00 | Space debris related activities in Russia | Vladimir Agapov(ROSCOSMOS) |
| 15:45 | New Space and the continued Need for Space Debris Mitigation | Stijn Lemmens(ESA) |
| 16:30 | 休憩 | |
| 16:40 | Brief Overview of the Current Status of Space Traffic Management | Christophe Bonnal(CNES) |
| 17:10 | Latest developments on space debris modelling activities at CNES | Juan-Carlos Dolado-Perez(CNES) |
| 17:40 | Modeling the space debris environment - latest improvements and updates | Carsten Widemann (TU Braunschweig) |
2月25日(木) 9:30開場
| 開始時間 | 講演タイトル | 講演者(所属) |
|---|---|---|
| 10:00 | 九州大学における宇宙デブリのモデリング | 花田俊也(九州大学) |
| 10:20 | 推移モデルを用いた宇宙機の軌道投入許容量の検討 | 長岡信明(JAXA) |
| 10:40 | JAXA独自のデブリ推移予測用ベースラインファイルの開発状況 | 河本聡美(JAXA) |
| 11:00 | 換気休憩 | |
| 11:05 | 低軌道ADRミッションにおけるターゲット物体の姿勢運動解析 | 松下悠里(九州大学) |
| 11:25 | 経済学からのデブリ問題分析 | 八田真児(MUSCATスペース・エンジニアリング) |
| 11:45 | 昼休み | |
| 13:00 | パネルディスカッション 「法政策的見地からのデブリ対策に対する産学官の役割」 |
モデレータ:竹内悠(JAXA) パネリスト: 新谷美保子 (TMI総合法律事務所) 大塚聡子(NEC) 渡邉亜希子(スカパーJSAT) 吉田良太(JAXA) |
| 14:30 | 休憩 | |
| 14:50 | アストロスケールが取組むRPO技術 - 低軌道デブリ除去から静止軌道での軌道上サービスまで | 岡田光信(アストロスケール) |
| 15:10 | 最近のスペースデブリをめぐる規制とSTMの最近のグローバルな議論について | 岩本彩(アストロスケール) |
| 15:30 | 低軌道デブリ光学観測システム | 柳沢俊史(JAXA) |
| 15:50 | 日豪2地点からの低軌道物体光学観測実証 | 中道達也(IHI) |
| 16:10 | 休憩 | |
| 16:20 | 静止衛星の測光・分光同時観測 | 藤原智子 (日本スペースガード協会) |
| 16:40 | ライトカーブ観測とH-2A R/Bモデルを用いた再現実験 | 黒崎裕久(JAXA) |
| 17:00 | 微小デブリ軌道上観測データの統計的解析手法 | 古本政博(東京都立大学) |
| 17:20 | デブリの軌道・回転運動把握のためのSLR反射器(Mt.FUJI)の開発 | 秋山祐貴(JAXA) |
2月26日(金) 9:30開場
| 開始時間 | 講演タイトル | 講演者(所属) |
|---|---|---|
| 10:00 | 衛星用複合材推薬タンクの再突入安全性評価モデル | 清水隆三(JAXA) |
| 10:15 | 高忠実な物理モデルによるリエントリ安全評価法LS-DARCの開発: 第2報 熱流束モデル検証プロセス | 藤本圭一郎(JAXA) |
| 10:40 | 換気休憩 | |
| 10:45 | デブリ衝突損傷リスク解析ツールTURANDOTの現状と改修計画 | 中渡瀬竜二(MUSCATスペース・エンジニアリング) |
| 11:05 | 次世代型宇宙用デブリモニタBBMの開発 | 松﨑乃里子(JAXA) |
| 11:25 | 耐AOコーティングによるCFRPからのイジェクタの低減 | 西田政弘(名古屋工業大学) |
| 11:45 | 昼休み | |
ポスターセッション(オンライン中継)
| 開始時間 | ポスタータイトル/発表者 |
|---|---|
| 13:00 |
|
| 開始時間 | 講演タイトル | 講演者(所属) |
|---|---|---|
| 13:35 | 換気休憩 | |
| 13:40 | ELSA-d, ADRAS-Jプロジェクト及び将来サービスのための地上システムと運用について | 小堀加奈絵(アストロスケール) |
| 14:00 | ELSA-d プロジェクト ステータス -打ち上げにむけて- | 岡本章(アストロスケール) |
| 14:20 | ADRAS-Jプロジェクト概要 -世界初大型デブリ除去実証技術とは- | 藤田勝(アストロスケール) |
| 14:40 | 休憩 | |
| 14:50 | デブリ環境改善に対するMHIの取り組み | 小早川豊範(三菱重工業) |
| 15:10 | 衛星搭載パルスレーザーによる軌道離脱サービス | 福島忠徳(スカパーJSAT) |
| 15:30 | スペースデブリ発生防止用導電性テザーシステムとその実証 | 江川雄亮(ALE) |
| 15:50 | デブリ除去に向けた1kW級ホールスラスタシステムの研究開発 | 張科寅(JAXA) |
| 16:10 | 換気休憩 | |
| 16:15 | ADR作業の為の非協力的ターゲット捕獲・把持機構の検討 | 中西洋喜(東京工業大学) |
| 16:35 | ロバスト性の向上を目指したデブリ捕獲機構のコンセプトと開発状況 | 谷嶋信貴(JAXA) |
| 16:55 | 動ターゲット捕獲検証プラットフォーム(SATDyn)の開発 | 岡本博之(JAXA) |
| 17:15 | ADR用銛機構の性能向上に向けた日本刀技術導入の検討 | 渡部武夫(神奈川工科大) |
| 17:35 | 閉会挨拶 | デブリワークショップ実行委員会 |
お問い合わせ先
スペースデブリワークショップ事務局
mailto: debris-ws9@chofu.jaxa.jp